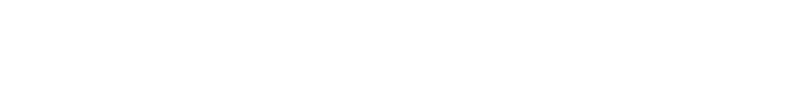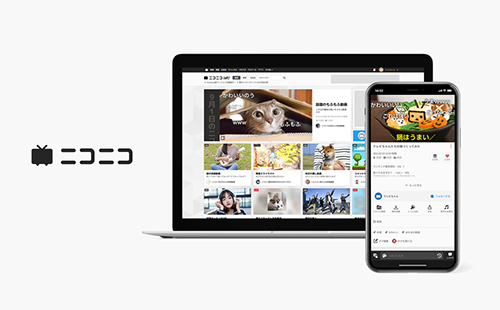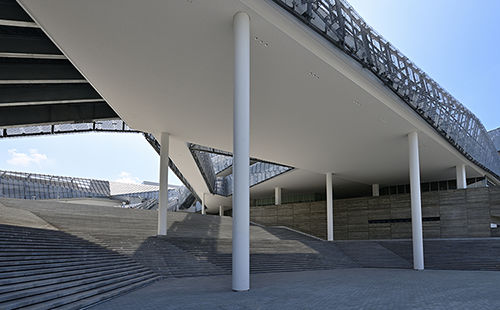なぜKADOKAWA本体が、あえてゲームを自社制作するのか──“原作愛”でIPの可能性を広げる、ゲーム事業局の挑戦
なぜKADOKAWAは、数々のゲーム子会社を擁しながらも、自社本体内でゲーム制作に取り組んでいるのか──その背景には、「ゲームはIPを“体験”へと広げるメディアである」という考え方があります。
年間6,000点超の書籍と40本以上のアニメ作品を世に送り出すKADOKAWA。その膨大な自社IPと非常に近い距離で向き合い、企画段階から深く関わりながらゲームを生み出すため、2023年に立ち上げたのが「ゲーム事業局」です。
この組織は、単なる開発部門ではなく、原作への理解と体験設計を軸に、IPの可能性を広げるためのチームとして位置づけられています。
今回、KADOKAWAゲーム事業局 局長の熊谷美恵さん、ゲーム事業開発部 部長の横山武司さん、ゲーム事業戦略部 部長の長谷川友洋さんの3名に、KADOKAWAならではのゲームづくりと、その背景にある想いを聞きました。
ライセンスアウトから「自らつくるゲーム事業」へ
「ゲームを、IPを広げるための新しい表現手段にしたい」
そう語るのは、ゲーム事業局のトップを務める熊谷さんです。キャリアをセガでスタートし、アーケードゲームやコンシューマーゲームのプロデューサーを歴任。その後、コロプラでスマートフォンゲームの開発・プロデュース、チームマネジメントに携わるなど、長年にわたってあらゆるプラットフォームの現場を見てきました。現在はゲーム事業局の統括責任者として、自社IPのゲーム開発の企画推進と、外部パートナーとの共創による新しい制作体制の構築に取り組んでいます。
「ゲームを起点にIPやコンテンツの可能性をどう広げていけるかを常に意識しています。」と熊谷さんは話します。
KADOKAWAはこれまで、スマートフォンゲーム分野においてライセンスアウトを中心としたビジネスモデルを採ってきました。リスクを抑えながら幅広いパートナーと連携できるメリットがある一方で、「ゲーム体験そのものへの責任」や「IPの継続的な成長にどれだけ貢献できているか」という観点がどうしても薄くなってしまうという側面もあったといいます。
「そこで近年は、自社でパブリッシング機能を整え、ゲーム事業の“中核”を自分たちの手に取り戻す方向に舵を切りました。モバイルゲームの自社事業化はその第一歩であり、KADOKAWAが持つ豊富なIP資産を、より一貫した体験設計のもとでユーザーの皆さんに届けていくことを目指しています」(熊谷さん)
社長直轄──“決めるまでの距離”が劇的に縮まった
KADOKAWAのゲーム事業局は、社長直轄の体制になっている点も特徴的です。
「ゲームの企画には、スピードと一貫性が求められます。社長直轄になったことで、現場の提案がすぐに経営判断につながるようになり、“決めるまでの距離”が一気に近くなったと感じています」
その体制により、新しいIPをゲーム化する際も、社内のアニメ部門や出版部門との連携を、経営層を介して横断的に進めることができるようになりました。
「“KADOKAWAとして何を届けたいのか”という視点が全員で共有しやすくなりました。現場も以前よりずっとスピーディに、かつ主体的に動けるようになっていると思います」

ゲーム事業局の役割は「IPと開発をつなぐハブ」
KADOKAWAグループには、『ELDEN RING』を手がけるフロム・ソフトウェアや、スパイク・チュンソフトといったゲーム会社も存在しています。その中で、ゲーム事業局はどのような役割を担うのでしょうか。
「フロム・ソフトウェアやスパイク・チュンソフトは、それぞれ強い個性と哲学を持った会社です。一方で私たちゲーム事業局は、KADOKAWAのIPをどう“ゲームという体験”につなげるかを考える役割を担っています」(熊谷さん)
原作やアニメなど、KADOKAWAの多様なコンテンツを起点に「この物語ならどんな遊びが生まれるだろう」と企画を設計し、最適な開発パートナーとチームを組む。いわば “IPと開発の橋渡し役” がゲーム事業局の立ち位置だといいます。
「グループの中でそれぞれの強みを活かしながら、KADOKAWA全体としてのゲーム価値をどう高めていくか──その一端を担っているイメージです」(熊谷さん)
ゲーム化するIPの選定基準とは──
膨大なIPを保有するKADOKAWAですが、そのすべてがゲーム化されるわけではありません。数あるIPの中からゲーム化する作品を選び出す際、3つの基準があるといいます。
「単に“人気作をゲーム化する”という発想ではなく、ゲームというメディアに適した体験を設計できるIPかどうかを起点に考えています。一つ目は世界観に“インタラクティブ性”を持たせやすいか。二つ目は魅力的なキャラクターが描かれており、長期的にユーザーと関係を築けるか。三つ目は海外展開を見据えたポテンシャルを持っているか──という軸で優先順位を立てています。“ゲーム化すること自体”を目的にするのではなく、“ゲームという表現手段が加わることで、そのIPがもう一段階広がるか”。そこを重視しています」(熊谷さん)

ゲーム業界では、特定ジャンルに強みを持つ開発会社もあれば、複数ジャンルを展開して市場の変化に対応する企業も増えています。その中でKADOKAWAゲーム事業局は、ジャンルではなく“IPに最適な体験設計”を起点としたアプローチを取っています。実際に携わるタイトルは、RPGからパズルゲームまで幅広く、作品ごとに最もふさわしいゲーム体験を選択しているのが特徴です。ジャンル選定について、熊谷さんはこう語ります。
「ジャンル選定の起点になるのは、まず“作品性”です。例えば、長谷川さんが担当している『盾の勇者の成り上がり』シリーズを題材にしたゲームの場合、“盾しか使えない”“ディフェンシブな立ち位置の主人公”という作品の特徴があります。その特徴を活かして『ではディフェンスゲームにしよう』と発想していったほうが、作品とゲーム体験の結びつきが自然になります。これは“プロだからこそ出てくる特殊な発想”というよりも、むしろ“期待を裏切らないこと”を大事にしている感覚に近いです。一般のファンの方が『盾の勇者だったら、タワーディフェンス的なゲームはしっくりくるよね』と感じるようなイメージを、あまり壊さずにきちんと受け止める。ユーザーがその作品に対して抱いている期待値やイメージに寄り添うことを重視して、ジャンルやゲームデザインを考えています」(熊谷さん)


“どれだけ長く好きでいてもらえるか”――KADOKAWA流のゲームの届け方
KADOKAWAはIP戦略として「LTV(ライフタイムバリュー)」を重視しています。これは単なる売上指標ではなく、「ユーザーとどれだけ長く関係を築けるか」という価値観で定義されており、ゲーム事業局もその考え方を前提に事業設計を行っています。
「私たちは、LTVを“ユーザーとの関係をどれだけ長く続けられるか”と言い換えて考えています。ゲームは、体験を通じてキャラクターや物語と世界観を共有できるメディアです。だからこそ、短期的なイベントや刺激ではなく、“この世界にもう一度戻ってきたくなる理由”を作ることが大事だと思っています。その上で、マーケティングや開発、運営チームが立場を超えて議論し、『どんな体験が長期的なユーザー価値につながるのか』を企画段階から考えていく。“体験設計としてのゲーム”という発想が、ゲーム事業局の根底にあります」(熊谷さん)
編集部・原作者との距離感が違う「裏設定まで相談できる」
KADOKAWAだからこそ実現できるゲーム制作とはどのようなものなのか、その答えの一つが、編集部や原作者との距離の近さにあります。
「ゲーム会社側の立場から見ると、編集部や作家との距離は、従来はかなり遠く感じられるものでしたし、実際に作家の方々と直接会う機会はほとんどありませんでした。しかし、KADOKAWAに来てから、その感覚は大きく変わりました」(熊谷さん)

こうした環境の中でゲーム制作に携わることで、作家ご本人や、その作家を長年支えてきた編集者の「生の声」を聞く機会が生まれたといいます。
「アニメ化され、商業的に大きく広がっていくほど、外部から作り手の顔は見えにくくなりがちです」と熊谷さんは前置きします。
「もう十分知られているIPだし、ビジネスとして軌道に乗っているから、これを前提に考えればいいだろう、と割り切ってしまってはならず、その源流にいる作り手の考えや想いを尊重し向き合わなければ、本当の意味でIPをちゃんとゲーム化することはできない、そう思っています」
ゴールがバラバラな中で、どう“一体感”を作るか
出版、アニメ、ゲーム──それぞれの現場には、それぞれのゴールがあります。それぞれのプロダクトのゴールが違うため、利害が完全には一致しない場面も生じます。
社内各所と何度もコミュニケーションを重ねながら、少しずつゴールをすり合わせていく──その積み重ねが、KADOKAWAらしいゲームづくりの基盤になっていると熊谷さんは語ります。
編集部との距離感も、一般的なライセンシー(IPを借りてゲームを作る立場)としてやりとりしていた頃とは大きく異なります。
「もちろんビジネスとしての線引きはありますが、“社内の人”という意識があるからこそ、親身になって相談に乗ってもらえたり、落としどころを一緒に探していただける場面もあります。一方で、言うべきことははっきり言ってもらえます。外部のライセンシーであれば、ビジネス上の距離感から憚られてしまうことも、社内だからこそ歯に衣着せぬフィードバックを受けることができます。その分、こちらも腹を割って話すことができ、『じゃあ一緒にもっと良いものを作りましょう』という前向きな関係になりやすいと感じています」(熊谷さん)
原作との距離の近さがつくる、KADOKAWA独自の開発体験
原作との距離感は、実際のゲーム制作現場にどのような影響を与えているのでしょうか。ゲーム事業開発部で開発を指揮する横山さんは、入社前に抱いていたイメージとのギャップをこう語ります。
「入社前は、ライセンシーとしてゲームを作っていた頃と大きな違いはないと思っていました。しかし、実際に携わってみると、原作との距離が想像以上に近く、その分IPの理解をより深め、より高いレベルでIP価値を意識する必要があることを強く感じました」
外部ライセンシーとしての立場では、原作者や編集者との距離がどうしても生まれ、ゲーム制作側が“推測”で判断する場面も少なくありません。一方で、社内で編集部・原作サイドと並走できる環境では、作品そのものへの理解を深めながら、より一貫した体験設計が行えるという大きな利点があります。
「作品によってスタンスはさまざまですが、ゲームオリジナルの設定やキャラクターの相談がしやすかったり、原作やアニメでは描かれていない“裏設定”をご提案いただけることもあります。IPとしての解像度を高めながらゲームを作っていけるのは、KADOKAWAならではの大きな魅力だと思います。それに、同じ社内だからこそ遠慮がないんです。 これは違う、ここはIPらしくない── ゲームに対してのフィードバックはかなり鋭いです(笑)」
原作者や編集部から寄せられるフィードバックは時に厳しく、IPのコアの部分に触れる指摘も多くあります。しかし、それこそが作品が本当に伝えたいメッセージに沿ったゲーム体験を作るための重要なプロセスになります。
「そのハードルを越えた先に、“ファンに届くゲーム”がある」と横山さんは語ります。

『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』に見る成功例
原作との“近さ”が、ゲーム開発において実際に大きな成果につながった例のひとつが、2022年11月にリリースした『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』です。アニメ第1期の放送が終了したタイミングの中で、「作品ファンの方々にどうやって継続的に興味を持ち続けていただくか」という課題がありました。
「ゲームの中で“ファンの方が喜ぶ展開”を継続していくために、パブリッシャーであるAimingさんと連携しながら、完全新作となるゲームオリジナルの長編シナリオを展開することになりました。 制作にあたっては、作品関係者や原作者の先生にもご協力いただき、原作キャラクターたちの新たな一面を丁寧に作り込んでいます。」(横山さん)
シナリオのプロットからセリフまで、すべて原作者に監修を依頼し「作品公認のオリジナルシナリオ」として展開。アニメ終了後にスタートしたこの施策は、大きなヒットにもつながりました。
「ゲーム内でしか見ることができないキャラクターの一面がシナリオだけでなくデザインとしても起こされることで、アニメでも原作でも見られない、“ゲームでしか触れられない体験”になっています。ゲームと作品との距離の近さと関係値は、KADOKAWAだから実現できた成功例だと考えています」(横山さん)

ゲーム化は“世界が立体化する”体験に――原作者の声
ゲーム化は、ファンやユーザーだけでなく、原作者にとっても新しい体験をもたらします。『陰の実力者になりたくて!』原作者の逢沢大介氏は、ゲーム化に際してこう語っています。
「ゲーム化されたことは本当に嬉しかったです。実際にプレイして、いちばん強く感じたのは“世界が立体化した”ということでした。小説は文字だけで表現するため、情報量が最も少なく、マンガやアニメでは絵や動きが加わって世界が広がっていきます。それでも“作品世界の一部のごく一部しか表現しきれていない”と感じていました。一方でゲームは、プレイヤー自身が能動的にその世界に入り込み、さまざまな角度から体験することができます。『あ、こんなふうに見えるんだ』という発見があって、作品世界がより具体的に立ち上がってくる感覚がありました。これはゲームならではの魅力だと思いますし、やってよかったと心から思っています」
一方で、ゲーム化には当初不安もあったといいます。しかし、その不安以上に、作品のファンからの温かい反応が届いたといいます。
「ゲームという以上、ガチャ要素もあり、否定的な声もあるのではと覚悟していましたが、それを含めて受け入れてくださる方が多かった。“自分の作品をこれほど肯定的に楽しんでもらえるんだ”と感じられたのが、何より嬉しい体験でした」(逢沢氏)


“文字だけで人を感動させているIP”を預かるということ
IPをゲームとしてどのように“体験化”するのかを考えるうえで、メディアごとの表現の違いを理解することは欠かせません。ゲーム事業戦略部でプロモーションを担当する長谷川さんは、小説、アニメ、ゲームという3つのメディアが持つ表現の違いをこう語ります。
「小説はテキスト一本で勝負するコンテンツです。アニメになると映像・テキスト・ボイス・音楽など表現の要素が増えていきます。そしてゲームは、そこに“触り心地”などの変数が入るインタラクションが加わるメディアです」

一見すると、ゲームは他メディアと比べて表現の幅が広いように思えます。それは同時にゲーム制作の難しさでもあると長谷川さんはいいます。
「オリジナルゲームを一から立ち上げようとすると、物語も面白くなければいけない、グラフィックも良くなければいけない、触り心地も良くなければいけない。さらに“新しい体験”まで求められる。『もう新しいものなんて残っていないのでは』と思うこともあります」
だからこそ、KADOKAWAでのゲームづくりには大きな強みがあると長谷川さんは続けます。
「すでに“文字だけで人々を感動させているIP”がベースにある。これは本当に大きいです。感動の核となる部分がすでに存在しているからこそ、ゲームでは“どう体験として立ち上げるか”に集中できる。それは開発する側にとっても、安心感やありがたさにつながっています」
長谷川さんは、入社前は“KADOKAWAのゲーム事業”に明確なイメージを持ちづらかったと話します。しかし、実際に働く中で、KADOKAWAならではの“スケール感”を強く実感したといいます。
「出版・アニメ部門と横断的に連携できるスケールがあるということです。たとえばマーケティングについても、アニメ宣伝や書籍宣伝の結果を踏まえながら企画できる。これは社内での一貫体制だからこその武器だと思います」
IPを未来へ広げるチームで働くということ
現在、ゲーム事業局は25名体制。平均年齢は40代と経験豊富なメンバーを軸に、さらなる体制拡充を進めています。
熊谷さんは、組織のカルチャーを踏まえながら、この組織で活躍する人物像についてこう語ります。
「ゲーム事業局には、ゲームだけでなくマンガ・アニメ・書籍など、エンタメ全般が好きなメンバーが多くいます。社内の社員の自己紹介ページでも“推し作品”を書く人が多いのですが、そういう“好き”の熱量を仕事に還元できる人が、この組織では生き生きと働いています。また、“自走する人”という言葉がよく使われますが、自分で動いて周囲を巻き込み、道を切り開ける方を歓迎したいですね」
さらに長谷川さんは、同局が特に求めている人物像について補足します。
「“ゲームが好き”という気持ちはもちろん重要ですし、それに加えてIPの文化的背景や、作品が持つ根幹の魅力を理解した上で、“それをゲームとしてどう咀嚼するか”を考えられる人。そういう視点を持つ方は、非常に相性が良いと思います」

では、KADOKAWAのゲーム事業局はどのような体制で動いているのでしょうか。長谷川さんは、その特徴を次のように語ります。
「外注管理中心の印象を抱かれやすいですが、実際には出版・アニメチームと横断的に連携しながら、一つの体験をつくれるスケール感こそが武器です。“コードを書くスタジオ”ではなく、制作・事業・宣伝・IP連携、それぞれに専門性を持つ“少数精鋭チーム”です。出社も在宅も柔軟に選べるので、働きやすさという点でもバランスが取れています」

横山さんは、若手からシニアまでの活躍機会についても触れます。
「ゲーム開発の経験があれば、若手でも十分に活躍できます。一方、中堅〜シニアの方であれば、事業面も含めて“自分で道を作っていける人”がよりフィットすると思います」
求められるスキルセットをこう続けます。
「若手の方でも、開発現場での経験があれば力を発揮しやすいです。 中堅〜シニアの方であれば、ゲーム事業をビジネスとしてプロデュースした経験があると、より早い段階から活躍しやすいと思います」
KADOKAWAのゲーム事業局は、単なる“ゲーム開発部門”ではありません。IPの本質を理解し、作品に敬意を払い、社内外のパートナーと連携しながら、企画から届け方までを一気通貫で設計する──そんな“IPを未来へ広げるチーム”として存在しています。
「すべてはファンのために」──ゲーム事業局が目指す姿
ゲーム事業局が発足して、まだ3年余り。しかし、その短い期間でKADOKAWAゲーム事業局は「ライセンスアウト中心」から「自ら企画し、自ら届ける」体制へと大きな転換を進めてきました。
その根底に流れているのは、どのメンバーも口にする「原作へのリスペクト」と、ユーザーとの関係を長く続けていこうとする姿勢です。
「最終的には、すべてファンの方のためになることをやっている──そう胸を張って言えるゲーム事業でありたいと思っています」(熊谷さん)
KADOKAWAの自社IPゲームづくりは、まだ始まったばかりです。 “原作愛”を軸に、どのようにIPのLTVを伸ばしていくのか。今後の展開にも注目が集まります。

※本記事は、2026年1月時点の情報を基に作成しています