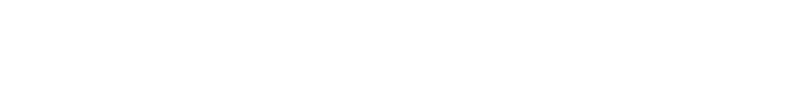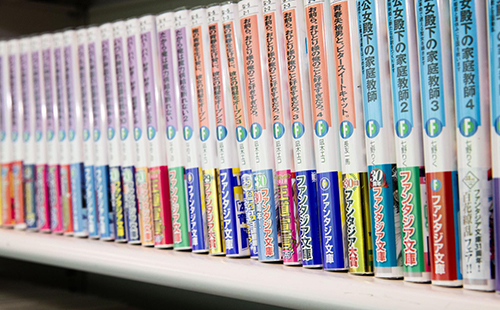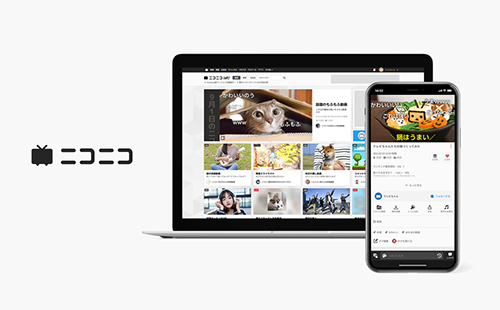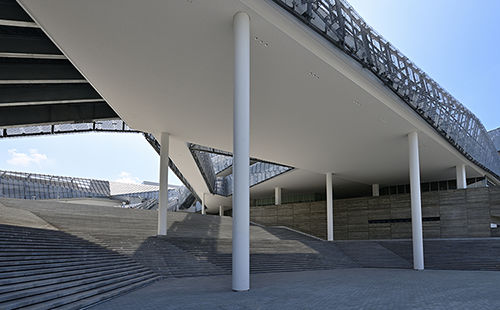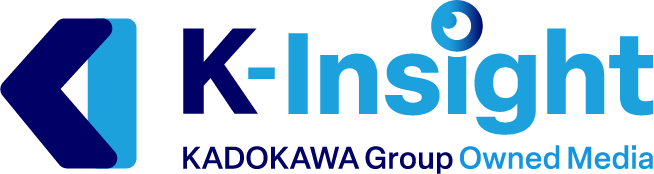子どもたちの“やりたい”が動き出す──「N Code Labo プログラミングサマースクール」体験レポート
KADOKAWAには、従業員が自発的に提案し、企画が通れば会社を横断したプロジェクトとして推進することができる「プロジェクト公募」という制度があります。その制度を活用して立ち上げられた「子育て支援プロジェクト」では、従業員自らが働きやすい環境づくりを考え、子育てに関する規定の改定をはじめ、交流イベントの開催など複数の新しい福利厚生サービスを実現しています。今回新たに導入されたのが、N高グループを手がける学校法人 角川ドワンゴ学園が運営するプログラミング教室「N Code Labo」の体験会料金や月額料金などの費用補助制度です。2025年夏には、その費用補助制度を活用できる、従業員の子どもを対象とした「N Code Labo プログラミングサマースクール」(以下、サマースクール)が開催されました。今回は、サマースクールでプログラミングに挑戦した子どもたちの熱い夏の体験をレポートします。
子どもたちの“やりたい”を叶えるN Code Labo
夏休みも終盤に差し掛かった8月20日、N Code Labo新宿校に子どもたちが続々と集まってきました。「N Code Labo プログラミングサマースクール」に参加する、小学6年生から高校1年生の皆さんです。用意されたのは3つのコース。ゲームプラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」で自作ゲームに挑戦するコース、より本格的な「Unity(ユニティ)」でのゲーム開発コース、そしてプログラミング言語「Python(パイソン)」を使ってAIを開発するコースです。学習期間も「1Day」と「3Days」から選ぶことができ、子どもたちの興味に合わせた幅広い選択肢が用意されていました。
「N Code Laboの強みは、なんといっても、子どもたちの『やりたい』を叶えてあげられるところです。日々新しい技術が登場するプログラミングの世界では、常に変化に合わせた学びが必要となります。だからこそ教材は原則として自作するとともに、その技術を教えるのが得意な講師をアサインする方針としてています。プログラミング教室は数多く存在しますが、ほとんどの教室が基礎的な内容までしか学べません。パソコンを使ったことがない初心者から、世の中に自分の作ったアプリを公開するプロ並みのレベルまで幅広くサポート出来る体制がN Code Laboの自慢です」と語るのは、N高グループが持つ個別指導系サービス(N Code Labo・N塾・個別指導コース)の立ち上げ及び責任者である 角川ドワンゴ学園 個別指導運営部 部長 佐藤 維人さんです。
少人数制指導でプログラミングを「特技」に
N Code Laboは東京・新宿のほか、秋葉原、横浜、大阪・梅田、天王寺にも教室があります。今回は夏期限定のサマースクールですが、「通学コース」や「オンライン個別指導コース」で継続的に学ぶことも可能です。最年少は幼稚園の年長から、上はなんと80歳以上の方まで、幅広い年齢層の生徒が教室に通っています。
週1回・約1年の学習で、プログラミングの基礎である「変数」「条件分岐」「繰り返し」「配列」の4要素が身に付きます。その先はオリジナルアプリの開発へ進み、SNSやブログで自分で制作した成果物のスマホアプリ・WEBサービスなどを公開する生徒も多く見られます。
「大学や企業から高く評価されるには、勉強しているだけでなく、実際に何かを<作っている>ことが大切です。そうした生徒は、受験や就職で有利になります。<興味がある>状態から<得意>へ持っていき、さらに自主開発ができる<特技>まで引き上げるには、どうしても少人数制の指導が不可欠なのです」(佐藤さん)

角川ドワンゴ学園 個別指導運営部 部長の佐藤 維人さん
この<特技>の段階まで到達すれば、副業として収益化したり、コンテストに挑戦したりと、次のステージへ進む生徒も増えてきます。
「自主開発できるようになれば、教室に通う頻度を減らして、その分浮く受講料などをクラウド運用費などに回してもらったほうがいいかもしれません。」(佐藤さん)
さまざまな受講のきっかけ。作りたいものが作れる環境がある
今回のサマースクールでは、各コース(Roblox/Unity/Python)に、その分野を得意とする講師を配置しました。3Daysの受講者は同じ講師が継続して指導する体制です。参加者に受講したきっかけを聞くと、「小学生の頃にScratch(スクラッチ)を学んで面白かったから」という声が多く聞かれました。一方で学年が上がるにつれて目的意識がはっきりし、「Pythonでより高度なAI開発に挑戦してみたかった」「画像認識を使ったユーザーインターフェースをPythonで作れると知って、実装までやってみたいと思った」といった動機で受講を決めた生徒もいました。



1Dayコースの講師を担った守屋 光晟さんが、N Code Laboのメリットとして強調するのは、「生徒が作りたいものを作れる環境が整っていること」です。「教材通りに進める生徒もいれば、自主制作で自由に開発する生徒もいます。そのどちらにも伴走ができるのはN Code Laboならではでしょう」(守屋さん)

N Code Labo講師の守屋 光晟さん
そして、こうしたサマースクールを通して感じてほしいのは、「うまくできて、楽しかった」という体験だといいます。「プログラミング自体に拒否感を持たないようにする指導を強く意識しています。タイピングが大変な部分もありますが、そこは全力で講師がサポートしますので、ぜひ成功体験を味わってほしいです」(守屋さん)
KADOKAWAでサマースクールの企画が立ち上がった理由
KADOKAWA 人事部の坂井奈菜さんは、企画の立ち上がりを次のように振り返ります。「子どもの夏休みなどの長期休暇中に、親として何かしてあげたいという社員の思いに、会社としてどのような支援ができるのか――「子育て支援プロジェクト」と共に、その検討から始まりました。その結果、当社グループに近いN Code Laboさんにご協力いただくことになりました」と話す。2024年夏と2025年春に行った長期休暇スクールでは、N Code Laboへの入会に結びついた例も生まれ、この施策をきっかけにプログラミングへの関心が高まった子どももいるといいます。
N Code Laboの佐藤さんは、KADOKAWAの福利厚生制度に採用されたという知らせを聞いたとき、「率直に嬉しかった」と振り返ります。その一方で、費用補助の使われ方には課題もありました。
「以前、クーポン型の福利厚生サービスを提供する会社でN Code laboをご紹介いただいた時にも一定の手応えがあり、AIへの関心の高まりがあるにもかかわらず本格的なプログラミングを学べる塾は少ないため、N Code laboのサービスは需要があると感じました。ただ、費用補助には上限があり、多くのご家庭では学習塾や英語、スイミングなど既存の習い事が優先されがちです。プログラミング教室は“第二の習い事”になりやすく、最初の選択肢としては選ばれにくいのです。そこで、長期休暇に合わせた短期集中のイベントに発想を切り替え、今回のサマースクールの企画につながっていきました」(佐藤さん)
難易度の高いプログラミングに挑戦する姿に保護者も驚く
3Daysコースの最終日には、プレゼン資料をまとめ、全員の前で受講した成果を発表する時間も設けられました。ある生徒がRobloxで形にしたのは、ゾンビが登場する「鬼畜ゲーム」。

N Code Labo生徒プレゼン資料より引用
「今後はもっと理不尽な要素を増やしたい」と話し、自分の世界観への強いこだわりを見せていました。
また別の生徒は、PythonでYouTubeの再生数を予測するAIに挑戦。条件分岐に基づく機械学習手法「決定木」を用い、さまざまな特徴量を与えて精度を高めていきました。

N Code Labo生徒プレゼン資料より引用
当初の予測スコアでは納得がいかず、説明文やタグなどから新たな特徴量を考えて追加したところ、さらにスコアを伸ばすことができたといいます。

「これまでは独学で学んでいましたが、AIを強くするには特徴量の組み合わせにも『相性』があると学べたのは新しい発見でした。将来は、プログラミングで食べていけるようになりたいです」とその生徒は語ってくれました。
スクールに参加したお子さんの保護者の方も、難易度の高いプログラミングに挑む様子に驚きつつ、次のような感想を話してくれました。「とても楽しめたようで、参加できて良かったです。参加者それぞれがやりたいことに取り組める環境が、子どもにとても合っていたと思います」
一番大事なのは、どんなものを作りたいかという「欲求」
N Code Laboの佐藤さんは、「今後さらに、教材をパワーアップさせていきたい」と抱負を語ります。
「実はKADOKAWAグループの中でも、特にドワンゴのエンジニアのお子さんが多く入会しています。ドワンゴはエンジニアの方も多く所属している会社ですので、ゲーム開発などを通して、ご自身のお仕事に興味を持ってほしいという親御さんの思いがあるからでしょう。今後は、KADOKAWAで働く親御さんにも刺さるような教材を考えていきたいと思っています。例えば、生成AIと一緒に書籍管理アプリを3日で作ってみましょう、といった身近で使えるテーマです。手元の課題に結びつけることで、プログラミングをより自分ごととして感じていただけるのではないでしょうか」(佐藤さん)
N Code Laboが提供するのは、単なるスキルの習得にとどまらず、その生徒の思考力や想像力を自由に羽ばたかせる体験です。今のプログラミングは、生成AIや各種API(※Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)=システムを繋ぐ接点や仲介となる仕組み)の進化により、より簡単に、より高度な開発ができるようになっています。だからこそ一番大切なのは、どんなものを作りたいかという「欲求」です。その欲求を確かな形に変えていけるのがN Code Laboという場所だと感じるサマースクールでした。



※本記事は、2025年10月時点の情報を基に作成しています