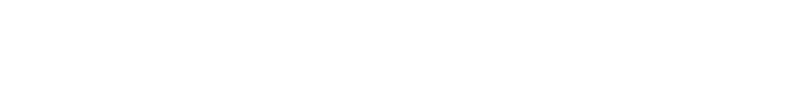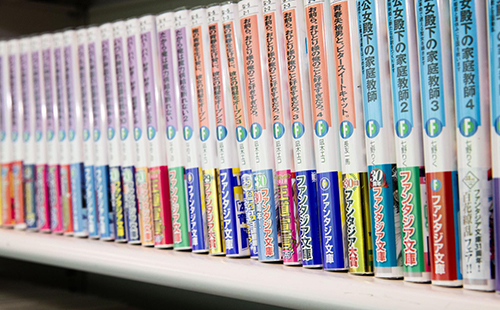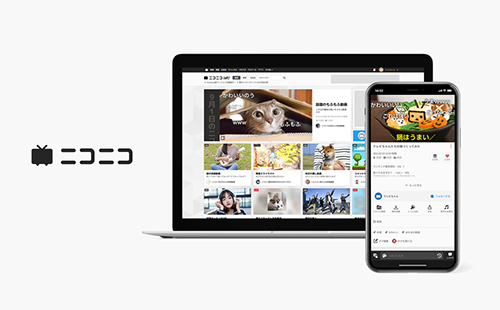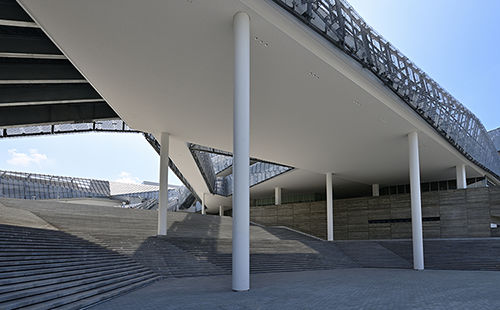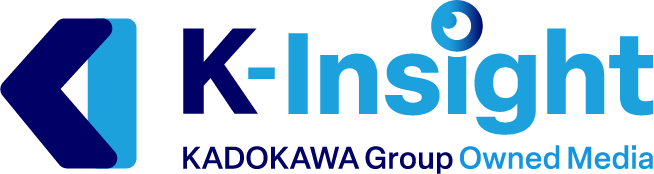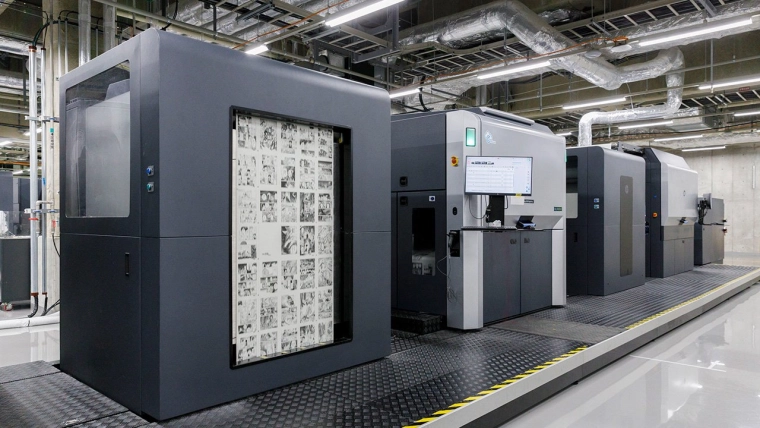編集者は生成AIといかに向き合うべきなのか?「出版事業グループAI研究会」が模索する新たな姿
出版社として生成AIをどう活用すべきなのか──。この問いに向き合うべく、KADOKAWAでは早くから独自の体制を整え、編集者のAIリテラシーの向上に取り組んできました。
その代表例がKADOKAWAグループ内の有志による「出版事業グループAI研究会」です。現在89名(2025年9月時点)が参加するこの活動では、編集者とエンジニアが協働しながら、主にAIを活用した編集業務の効率化を模索しています。根幹にあるのは、革新的な技術を通じてクリエイターの創造性やコンテンツの魅力を最大限引き出すという考え方です。クリエイティブな活動に、より多くの時間と労力を注げる環境づくりに取り組んでいます。
同研究会の発起人である伊集院元郁さん(KADOKAWA 児童・教養局 学芸ノンフィクション編集部 学芸図書課 編集長)と、技術面でサポートする塚本圭一郎さん(KADOKAWAデジタルマーケティング局 データマネジメント部 部長、ドワンゴ 技術本部 Dwango DataManagement Service部)に詳しい話を聞きました。
AI研究会という新たな挑戦
──出版事業グループAI研究会(以下、AI研究会)がどのような活動をしているのか教えてください。
伊集院さん:AI研究会は2024年4月に発足し、ライフスタイル、エンターテインメント、児童書、ノンフィクションなど異なる書籍ジャンルを担当する約60人の編集者に、サポート役としてドワンゴなどKADOKAWAグループ内のエンジニアやデータ活用の専門家などを加えた構成となっています。
「研究会」という名前は付いているものの、活動自体は非常にカジュアルに行っています。基本的なコミュニケーションの場は社内のコミュニケーションツールとして使用しているSlack上のチャンネルで、各自が実践する生成AIの活用方法や新たな発見などを投稿・共有してもらっています。また、私がMCを務める月1回のオンライン定例会では、AIに関する最新の業界動向や著作権との向き合い方に参考になるような情報を紹介して、メンバー同士で意見を交換することもあります。
いち早くガイドライン策定に動き始めた
──生成AIの活用に慎重な企業も多い中、KADOKAWAではどのような体制で取り組まれているのでしょうか?
伊集院さん:出版社として生成AIを活用するにあたって、どういった範囲であれば生成AI特有のリスクとの間でバランスがとれるのかは悩みどころです。当社には従業員向けのAIガイドラインがありますので、その拡充と並行するかたちで、このAI研究会をスタートさせました。ガイドライン策定の中心的な役割を果たしているのが、塚本さんです。
塚本さん:AIガイドライン策定に取り組み始めたのは、生成AI元年とも呼ばれる2023年です。この年は、OpenAI社が開発するChatGPT以外にも各社の高性能な生成AIのリリースが相次ぎ、世界中で利用者が急増しました。KADOKAWA社内でも生成AIの利用ニーズが高まるだろうと想定し、すぐにガイドラインを作成するプロジェクトを立ち上げたんです。

KADOKAWA デジタルマーケティング局 データマネジメント部 部長、ドワンゴ 技術本部 Dwango DataManagement Service部 塚本 圭一郎さん
まずは政府のガイドラインなどを参考にしながら私が作成したドラフト版を経営陣にレビューしてもらったのですが、クリエイティブに対する活用には非常に慎重だった一方、従業員が抱える業務の効率化についてはポジティブでした。一人あたりの生産性が10%向上するだけでも自社にとっては非常に大きなインパクトになります。業務上のメリットをよく理解されていたからこその受け止め方だったと思います。
その後、議論を重ねてできあがった完成版ガイドラインは、ChatGPTの利用に関する内容に絞った非常にシンプルなものとなりましたが、原則として生成AIで作成したコンテンツを最終的な成果物として使用しないという方針を定めていました。当然、契約している生成AIサービスは企業向けのプランですから、入力したデータが学習され、情報漏洩するということもありません。また、2025年度には、ChatGPT以外の生成AIサービスにも適用できる利用ガイドラインにアップデートした上で、生成AIで作成したコンテンツを最終的な成果物として使用したい場合の相談窓口を立ち上げています。
社内イベントが変えた編集者のAI観
──そもそも、どのような経緯でAI研究会は立ち上がったのですか?
伊集院さん:2023年5月にグループ従業員向けに開催されたイベント「大規模言語モデル(ChatGPTなど)ハッカソン・アイデアソン」がきっかけとなりました。それまでLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)や生成AIを編集者の仕事に結びつけて考えたことはなかったんですが、募集要項に「LLMやその周辺サービスの性質を正しく理解し利用できるようになるということは、今後のビジネスの上で、〈インターネットを利用できる〉レベルの必須スキルになる可能性がある」と書かれており、とても興味をそそられました。
塚本さん:「ハッカソン」は実際に動くアプリケーションやサービスを短時間で開発するイベントで、「アイデアソン」はアイデアの創出を目的としたイベントです。伊集院さんが参加されたのはアイデアソンのほうですか?
伊集院さん:そうです。この時は「青空文庫」などインターネット上にある著作権保護期間の満了したテキストを使って、生成AIがどの程度日本語を扱えるのか、編集者目線で検証してみました。漢字に読み仮名を振ったり、文体を変更したりといった処理を試すと、想像以上に精度の高い結果が得られました。驚きましたし、同時に可能性を感じました。
イベントでは「アイデア/実験報告部門」で入賞することができ、そこでいただいた賞金で複数の生成AIサービスの有料プランに加入しました。アイディアソンでやったような検証を続けて編集部の中で共有したり、局内の事例共有会でプレゼンしたりしているうちに当時の局長が目をとめてくださって、「せっかくなので予算化しましょう」と。それで2024年4月に正式にAI研究会として発足することになったんです。
アイデアの作り方そのものを学び合う場に
──AI研究会の活動はどのように変化してきたのでしょうか?
伊集院さん:AI研究会で最初に設定した目標は、参加する編集者が生成AIを楽しむこと。そこで出したお題は「ChatGPTと会話をして、おもしろいと思った会話、すごいと思ったこと、驚くべき会話の内容を共有してください」というものでした。扱い方に慣れてきてからは、プロンプト(AIに対し、ユーザーが入力する指示や質問)のコツを共有しあう方向にシフトしました。メンバーの習熟が進んだ現在では、編集者がAIとどう付き合っていくべきかを一緒に考え、AIリテラシーを互いに高め合うための場にもなればよいな、と考えています。

KADOKAWA 児童・教養局 学芸ノンフィクション編集部 学芸図書課 編集長 伊集院 元郁さん
塚本さん:私も技術的なサポートの立場でAI研究会に参加しており、最初こそプロンプトのコツをお伝えしたりしていましたが、いまはその機会はあまりないですね。私たちエンジニアより使い倒している編集者の方もいるくらいですから。日々テキストに触れてきている方々だからこそ、生成AIの特性や限界を的確に理解されているんだと思います。
──より具体的にはどのような活用方法が研究会で共有されているんですか?
伊集院さん:活動の初期から試みられているのが、企画立案のためのリサーチです。編集者自身のアンテナや直感が大切なのはこれからも変わりませんが、自分ひとりでは気づかなかった視点から情報を集める、あるいは情報収集のスピードを速めるという部分で、生成AIは役立っています。
個人的におもしろいと思ったのは、生成AIを使った架空のカスタマーインタビューでした。実用書担当のある編集者は、企画が想定する読者の役をAIの側に設定し、このAIと対話していくことで読者ニーズを探り、そのイメージを固めていく、という方法を試みていました。
また、編集者自身が立案したタイトルやキャッチコピーの候補をAIに評価させることで、発想が深まる、判断基準を多角化することができる、という報告もあります。
こうしたアプローチを共有してもらうことで、同僚の編集者が頭の中でどのように企画を組み立てているかが見えてくることも、研究会の副産物でした。いわば思考のプロセスを覗き込むようなものなので、思わぬ勉強になる。生成AIの使い方を学ぶと同時に、研究会は、アイデアの作り方を学び合う場にもなっている気がします。
ほかにも、語学書の編集者なら、英単語の難易度に応じて例文集の順序を並び変える、という作業を試してみる。料理本の編集者なら、使われている材料から日本食品標準成分表にもとづく栄養素計算をさせてみる。学術書の編集者なら、参考文献表の表記を特定の形式に揃える作業をさせてみる──。
こういった検証を、研究会のメンバーが自分の専門ジャンルでおこなっているので、自然と、AIの処理を編集者の目で厳しく精査することになります。その結果、「このタスクの精度はまだ実用的ではないね」とか、「後工程で人間が校正をすれば、役立つかもしれない」、「この使い方は他の方法に応用できるかもしれない」といった、リアルな知見が蓄積されています。
普段はまったく異なる編集部に所属する編集者が、AIというテーマで横のつながりをもつことができていることも、「有志の研究会」という枠組みのメリットですね。
テクノロジーとクリエイティブが共存するKADOKAWAのカルチャー
──KADOKAWAにおけるAIの利用状況はいかがですか?
塚本さん:社内全体のAI利用率は指数関数的に伸びています。例えばSlackに統合したAIチャット補助を通じて、社内業務に関する情報を一元的に検索・取得できる仕組みがあり、これを使って「福利厚生は何があるか」「産休に入りたい」「PCをWindows端末からMacに変えたい」などの手続きを探すために利用されていたり、オンライン会議ツールのGoogle Meetの文字起こし機能をはじめ、業務効率化のためにAIが日常的に活用されている状況です。組織的な取り組みとしては、一番規模の大きい伊集院さんのAI研究会以外にも各局で勉強会が多数開催されており、全社的にAI活用への関心が高まっています。
伊集院さん:やはりそれは、塚本さんのようなエンジニアの方がグループ内で身近にいてくださるからでしょう。1年半前のAI研究会の立ち上げの際も、技術に詳しい方のサポートがなければ、情報漏洩や著作権侵害のリスクが不安で踏み出せなかったと思います。エンジニアの方々に気軽に相談できる体制があるかどうかで、企業の生成AIへの取り組み方は全く変わってくるんじゃないでしょうか。
塚本さん:社長の夏野さんがいろいろな場面でクリエイティブとテクノロジーの掛け合わせについて語っていることが、KADOKAWAにはプラスに働いているように感じます。社内にエンジニアチームがあって、クリエイティブな人材も豊富にいる。この両輪が揃っているのは、私たちの大きな強みですよね。
避けては通れないAIとの未来に向き合う
──生成AIの活用は今後どのように進んでいくと思いますか?
塚本さん:この流れが止まることはないでしょう。すでに多くの企業がAIとの共存を前提とした事業戦略を立て、実際に成果を上げ始めているところもあります。いずれスマートフォンのように、使わない選択肢がないレベルまで浸透していくはずです。
──その時、編集者はどうあるべきなのでしょう?
塚本さん:私が部長を務めるデータマネジメント部は、「AIにはできない人間のコンテンツ世界を明らかにする」というビジョンを生成AI登場以前から掲げてきました。AI技術を徹底的に活用し、技術的な限界を理解することで、逆に人間にしか実現できない価値の輪郭が見えてくる。そうして初めて、人間が本当に力を注ぐべきクリエイティブな領域が明確になります。
人間の仕事を置き換えるでも、コンテンツを大量生産するでもなく、あくまで人間のためにAIを使い倒す。AIの活用がさらに進む未来に備えて、こういった考え方がより重要になってくると思います。

伊集院さん:私も同感です。加えて、著作物を守るという編集者の大切な立場を忘れてはいけないなとつくづく思います。作品が世の中に出る際、作品と社会の接点に立ち会い、そこに責任を持つのが編集者です。新しい技術に対する、作家やクリエイターの懸念や問題意識を肌で感じ取り、理解することが欠かせません。
その意味でも、生成AIをめぐる法律や倫理といった問題についても互いに情報共有することで理解を深め、話し合い、より発展的なAI活用の方法が議論できるAI研究会のような場が社内にあることは非常に大切だと感じています。
※本記事は、2025年10月時点の情報を基に作成しています