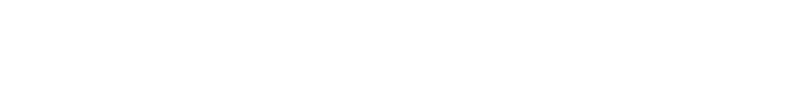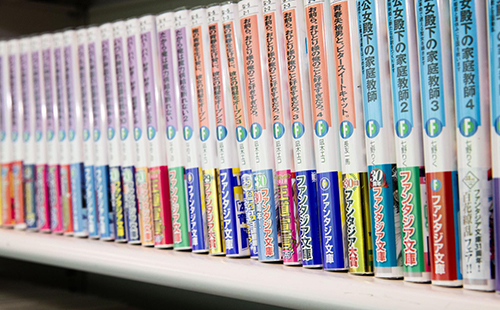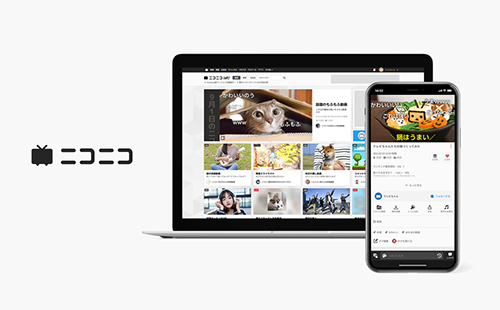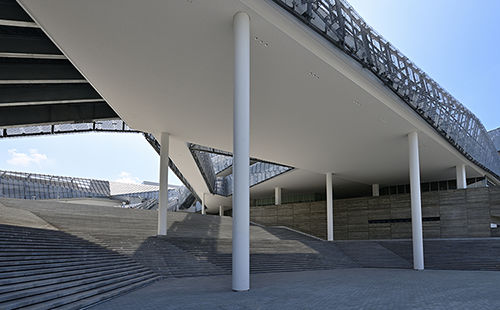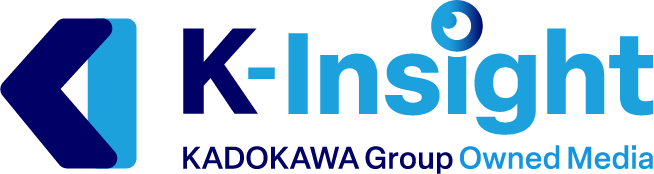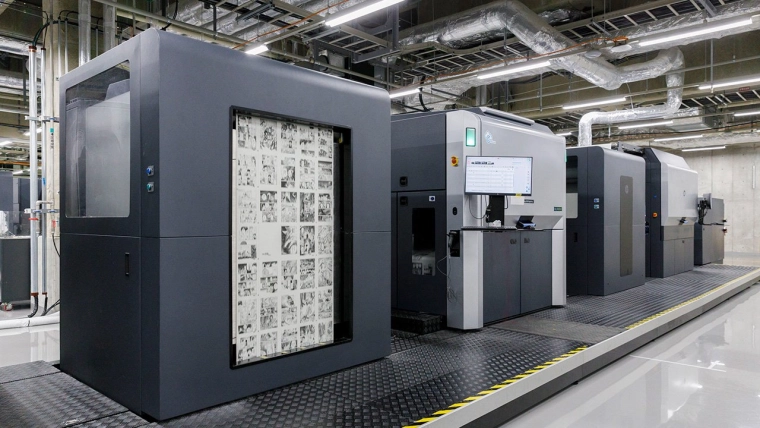N高グループを支える教育コンテンツ開発【前編】 ネットの中に“学びの場所”をつくる――「ZEN Study」が目指す、学びの本流とは
N高等学校・S高等学校・R高等学校(以下、N高グループ)やZEN大学で活用されている学習システム「ZEN Study」。その教育コンテンツの責任者を務める、コンテンツ開発部 部長・甲野純正さんは、予備校講師を経て46歳でドワンゴに入社しました。以来、かつて“学歴”に悩まされた自身の経験をもとに、理想の教育コンテンツとは何かを追い求めてきました。「ネットの中に “学びの場所”を作りたい」と語る甲野さんに、これまでのキャリアと「ZEN Study」に込めた思いを伺いました。
学歴に悩まされた過去。予備校講師の経験を生かしドワンゴに入社
――教育コンテンツの責任者である甲野さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
甲野さん:
実は私、大学受験で二浪していまして、最終的に合格したのは第4希望の大学でした。進学先は地理学科だったのですが、そこで出会った恩師の影響で、勉強嫌いだった私が研究の道を目指すようになりました。ところが、いざやってみると、その道にはまったく向いていなかったんですね。
大学院を修了した後、将来に悩んでいたところ、アルバイトでやっていた予備校講師の仕事にそのまま就職することにしました。その後は、地理の予備校講師としてフリーランスで活動し、西日本を中心に教壇に立っていました。
ただ、それだけでは物足りなくなり、もっと自分のキャリアを広げたいと思って、さまざまな仕事に挑戦しました。あるとき、一念発起して、全国的に学習塾を展開する企業に入社し、ネット上でライブ授業の配信を行っていたのですが、思うようにいかず、行き詰まってしまったんです。
そんな折、知人から「お前のやりたいことは全部ドワンゴにあるよ」と言われたんです。それをきっかけに、ドワンゴを受けて、無事に採用してもらうことができました。それが2016年2月、私が46歳のときです。
ちょうどその1カ月後、2016年4月に「ZEN Study」の前身である「N予備校」がスタートしました。私はそこから教育コンテンツの制作に関わるようになり、現在に至ります。
ネット空間の中に「学びの場所」を作る。「ZEN Study」の本質は「学校」であること
――ドワンゴに入社してみて、そこに「やりたいこと」がありましたか?
甲野さん:
その答えが見えてくるまでには、意外と時間がかかりました。最初の頃は、他社の教育サービスと競合しているつもりで、一生懸命取り組んでいたのですが、やがて「そうじゃない」と気づいたんです。
私が本当にやりたかったのは、ネット空間の中に「学びの場所」を作ることだったんです。たとえば、母校の前を通ると、懐かしい思い出がよみがえって、なんだか鼻がツンとする――あの感覚を、オンラインでも生み出せるのではないかと思っています。
「ZEN Study」の本質は、「学びの場所」であることであり、そしてその「教育の本流」を築いていくことだと思っています。
生徒との交流も大きく影響しています。教育コンテンツを作るにしても、「画面の向こうのよく知らない人」に届けているわけではありません。ある生徒と「ニコニコ超会議」の会場で行うN高グループの文化祭で実際にお会いした時に、「やっと会えた」と涙を流してくださったことがありました。その経験から、本当に届けなければならない人にきちんと届けられているかどうかを、強く意識するようになりました。
「生徒の自律的な学び」という理想を追求。誰もが自己ベストを目指せる環境を
――実際に、教育コンテンツを作るお仕事とは、どんなものなのでしょうか。
甲野さん:
我々がただ教育コンテンツを作って満足するだけでは、意味がないんです。それを使ってもらえるかどうか、そして成果につながっているかどうかが大切なんです。私たちは「作るのは“当たり前”、使ってもらって“よかったね”、学びの成果が出たら“おめでとう”」というスタンスで取り組んでいます。

ドワンゴ 教育事業本部 コンテンツ開発部 部長 甲野純正さん
「使われているかどうか」はログを見ればすぐにわかりますが、「学びの成果」をどう測るかは、今まさに格闘しているところです。「ZEN Study」の教材を使って学んだ生徒が習熟度テストを受けた際に、その結果を外部模試と連携させるなどして、独自のスコア化を試みています。これによって、TOEICのように点数だけで、学力の伸びを可視化できるようになると考えています。
「ZEN Study」は、N高グループやZEN大学に通う数万人規模の方に利用してもらっているので、私たちのもとには非常に大きな学習データが集まってきます。だからこそ、こうした新しいチャレンジも実現できるのではないかと思っています。
もちろん、難関大学を目指す生徒にきちんとした指導ができることは非常に重要ですが、全員が難関大学を目指すわけでもありません。しかし、「自己ベストを目指す」ことは誰でもできるはずです。正しく自分と向き合い、自分自身で課題を見つけて解決し、次の学びにつなげる。こういった習慣を身に付けることの方が、はるかに重要だと思っているんです。
その意味でも、学校のオンライン教育は、塾などとは異なり、「生徒の自律的な学び」という理想を徹底的に追求できる環境です。その理想を追い求めたコンテンツ作りをしていけばいいだけとも言えるので、むしろやりやすいかもしれませんね。
――甲野さんの中には、どのような理想があるのでしょうか。
甲野さん:
私にとって、「アダプティブラーニング(適応型学習)」という考え方は、教育コンテンツの理想を考える上でもひとつの大きなキーワードになっています。つまり、生徒一人ひとりの学力や理解度に応じた学びを提供するということです。例えるなら、視力検査のようなものです。最初に1.0の視力表を見せて、見えなければ0.8に下げ、逆に見えたら1.2に上げていきますよね。それと同じで、テスト問題もその生徒に合わせて違うものになる。カンニングも意味をなさなくなるでしょう。
N高グループやZEN大学には、非常に多様な背景や興味を持つ生徒や学生がいます。だからこそ、こうしたアダプティブな学びの仕組みを、プログラミング講座や動画クリエイター講座などのクリエイティブな授業にも応用できるか模索していきたいですね。
そのほかにも、病気で入院して通学できない院内学級の生徒や、さまざまな理由で高校に行けず大学入学資格検定を目指す生徒たちなど、学びに制限がある状況でも、きちんと学べる環境を提供していきたい――そんな思いも私の中にはあります。
受験地獄は幻想に過ぎない。生徒の皆さんは自由に生きて、好きなことをやってほしい
――さまざまな学力を持つ生徒に合う教育コンテンツを作るのは、非常に難しそうです。
甲野さん:
そうですね。私自身、気をつけているのは、生徒の希望にただ寄り添うだけのコンテンツにはしないということです。限られた学習時間の中で、やはり「この段階は乗り越えてほしい」というステップがどうしてもあるからです。ただ、そのバランスを取るのが非常に難しい。
今の学校教育は、偏差値によってある程度レベル分けされてしまっています。そのため、高い偏差値の学校でうまくいった学習方法が、他の学校でも同じように参考になるとは限りません。N高グループやZEN大学には、本当にさまざまな背景や学力の生徒や学生が集まってきているので、ある意味「日本社会の縮図」のような場所なんですね。だからこそ、ここで得られる学習データには、非常に大きな意味があると考えています。
しかし、私たちが目指している理想は、まだまだ先にあります。100年以上経ってもいまだに完成していない「サグラダ・ファミリア」と同じで、私の次の世代へバトンを渡していくようなイメージを持っています。焦らず一歩ずつ確実に進めていきたいですね。
――最後に、これから「ZEN Study」で学びを深めていく生徒・学生の皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
甲野さん:
私自身、「学歴とは何か」という問いに長い間苦しめられてきました。その呪縛から30歳を過ぎて解放され、ようやく今、こうした考え方を持てるようになりました。もし18歳の私が今と同じ考えを持てていたら、どんな人生が拓けていただろうかと考えてしまいます。N高グループの生徒やZEN大学の学生の皆さんは、きっとこれからその「30年先の景色」を見ていくのでしょう。

受験地獄というものは、日本の社会が勝手に作り出した幻想にすぎないと思うのです。生徒・学生の皆さんには、もっと自由に生きて、好きなことをやってほしいと心から思います。その輝いている皆さんを、きっと社会は見つけてくれるはずです。
※後編記事はこちらをご覧ください。
N高グループを支える教育コンテンツ開発【後編】VR空間で“友達”になる――「ZEN Study」がつくる新しい「学びと交流の場」
※本記事は、2025年10月時点の情報を基に作成しています