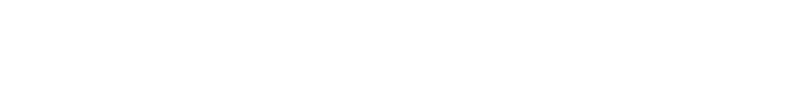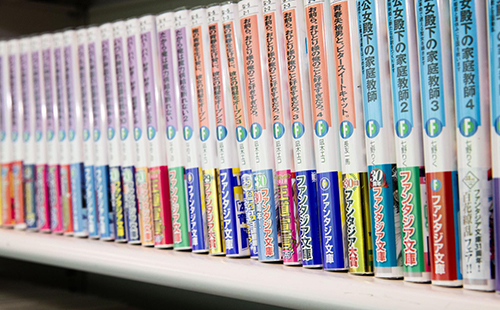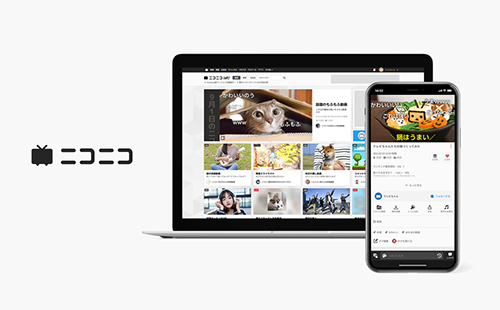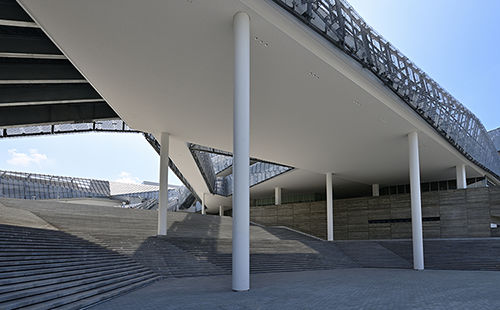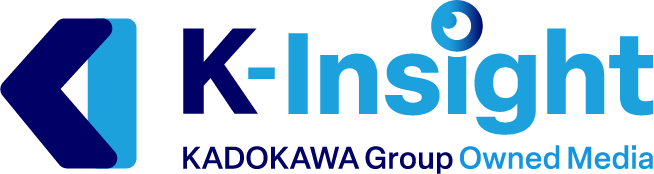世界中から応募が殺到した「ワードレス漫画コンテスト」。KADOKAWAが仕掛ける海外作家の発掘プロジェクトの舞台裏
KADOKAWAでは、多様なIPを安定的に創出し、世界に広く展開する「グローバル・メディアミックス with Technology」を基本戦略とし、メディアミックスの源泉である出版IPの創出力強化をグローバルで推進しています。
その取り組みのひとつとして、2022年10月よりKADOKAWAグループ全体の従業員から海外事業に関するアイデアを公募する「グローバルビジネス・アクセラレーション・プログラム(以下、GAP)」がスタートしました。
このプログラムでは、従業員の自発的な提案を主軸に、世界に向けたイノベーションの創出に取り組んでおり、これまでも、KADOKAWAで発行するアニメ情報誌「Newtype」を通じて日本のコンテンツを世界へ届けるプロジェクトや、国内外の名著コミカライズプロジェクトなどが実現に至っています。
そんな中、2023年度にGAPで採択されたのは「ワードレス漫画コンテスト」。“グローバルな作家の発掘を目的とした新しい漫画賞”として、プロジェクトは始動しました。
記念すべき第1回目の「ワードレス漫画コンテスト」は、2024年10月から約5カ月間にわたり実施され、世界104の国と地域の漫画作家から、応募総数1,126件もの作品が寄せられました。世界の漫画作家の「熱意」や「制作力」の高さを知る機会にもなったコンテストの舞台裏や今後の展望について、プロジェクトメンバーである岡村 華子さん、瀬川 昇さん、富崎 理紗さんの3人に話を聞きました。
海外の作家をいち早く発掘し、漫画家デビューにつなげたい
── はじめに、今回の「ワードレス漫画コンテスト」を企画した背景を教えてください。
岡村さん:私が所属する海外事業グループでは、国内外のグループ会社で働く方を対象に、誰でも応募できる海外事業に関するビジネスアイデアコンテスト(※GAPのこと)を主催しています。そこで集まったアイデアの中から、事務局が有望だと判断したものをいくつか選定し、平均3、4人程度のチームを作ります。そこから半年ほどかけてアイデアをブラッシュアップし、最終的には社長や役員を含む経営層に向けてプレゼンテーションを行っています。
今回の「ワードレス漫画コンテスト」は2023年度に採択されたアイデアで、プロジェクト化と同時にメンバーの皆さんには兼務という形で海外事業グループにも所属していただき、プロジェクト推進にあたっていただきました。
富崎さん:このプロジェクトがGAPとして動き始めた当初は、私は海外事業グループではなく宣伝局に所属しており、当時仕事で関わることが多かった編集の方に誘われて、このプロジェクトに参加しました。グローバル向けの漫画賞を企画したのは、国内の優秀な作家さんの獲得競争が激化している状況が背景にあります。漫画が描ける人はとても需要が高く、他出版社との“取り合い”になっていることから、有望な作家さんを国内では獲得しづらくなってきています。そのため、日本の出版社から声のかかっていない海外の作家さんをいち早く発掘し、関係性を築くことで、新たな漫画作品を生み出す一番最初のきっかけを作ろうと考えたのが、今回の漫画賞の根本的な狙いでした。

海外事業グループ グローバル電子書籍事業室 兼 海外マンガ編集部 富崎 理紗さん
また、言語に依存せずにどの国からでも応募しやすくし、審査側にとっても言語に左右されずに画力で評価できるようにするため、「ワードレス(セリフや書き文字のない漫画)」の形式にしたんです。
瀬川さん:今回のプロジェクトでは、KADOKAWAグループでも複数部署が横断して関わっており、GAPで「海外クリエイター探索と獲得」を行い、グローバルコミック編集部や協力してくれる出版事業グループの各編集部で「獲得したクリエイターの作品編集、商品化」を実施するといった連携を行っています。
私が管轄しているグローバルコミック編集部は、海外の現地のトレンドや好みに合わせた漫画の制作開発と、海外漫画IPの日本市場における翻訳出版展開を手がけており、今回の取り組みと非常に親和性がありました。
コンテストで発掘した作家に対して、グローバルコミック編集部で持つノウハウにより、海外作家の日本向けの「作品開発」をフォローし、加えて、世界をターゲットにした「出口戦略」を具体的に推進できるため、継続的にグローバル展開へとつなげる活動がしやすいことも、GAPで今回のプロジェクトが採択された理由のひとつだと思っています。
── ワードレス漫画コンテストの反応はいかがでしたか?
富崎さん:率直に、「海外作家からこんなに需要があるんだな」というのを発見できたのが大きな収穫でした。海外の作家さんたちは日本と違い、漫画賞などに応募する機会が少なく、「実は描ける人がたくさんいるのに、発表の場がなかった」という気づきを得られました。今回の漫画賞が、そういったニーズにうまくマッチしたのはとても良かったと感じています。
瀬川さん:絵のクオリティにおいても、当初は国ごとの地域性や特徴が出るのではと思っていました。しかし、いざ蓋を開けてみると、意外にも受賞者の方々は日本スタイルの右開きの横読み版面の漫画に馴染んでいたのがとても嬉しかったです。
私自身、マンガ編集歴が20年ほどになりますが、15年くらい前はまだ各国の漫画やアニメの表現がそれぞれ独自性を保っていた印象でした。それがスマートフォンの普及によって、誰でも気軽に日本の漫画を読むことができるようになり、世界的に日本の漫画のシェアが高まってきています。今回のプロジェクトを通して、日本の漫画のスタイルが世界で当たり前のように受け入れられてきたことを実感することができ、我々のIPを原作としたメディアミックスなどもしやすくなっていると感じました。
想像以上にクオリティの高い作品が多く、アルジェリアやアンゴラなどからの応募も目を惹いた
── このプロジェクトを推進していく際の苦労やエピソードがあれば教えてください。
富崎さん:これまで、KADOKAWAの国内本社から世界に向けて直接アプローチする施策はほとんどなく、海外向けのコンテストを一から作り上げる必要があったことから、すべてが手探りの状態から始まりました。文化的な違いやそれに伴う配慮なども含め、あらゆる面で慎重に考えながら設計していく必要がありました。
大変だった部分も多かったのですが、試行錯誤しながら周囲を巻き込み、一緒にコンテストの設計を作り上げていく感覚はとてもやりがいを感じていましたね。
瀬川さん:コンテストの審査自体はKADOKAWAのコミック編集部に依頼しました。単なるコンテストで終わるだけではなく、受賞者にきちんと「作家デビュー」という出口を提供したいという想いから、我々の覚悟として「選んだ作家は必ずデビューさせてほしい。もしそれができないなら審査自体しなくて構わない」という約束をさせてもらいました。
正直なところ、その約束については編集部からの反発を覚悟していましたが、意外にも前向きに捉えていただいたのは有難く感じています。そういう見えない部分の細やかな調整は大変だったものの、最終的にはコンテストの設計として、受賞者の連載枠を確約する形にできて、とてもよい形にまとまったのではと思っています。
富崎さん:また、応募作品について印象的だったのがアルジェリアやアンゴラなどの国々からの応募です。アメリカや台湾などからの応募は一定数あるだろうと予測していましたが、あまり応募が来ることを想定していなかった国や地域から想像以上にクオリティの高い作品が寄せられたことには驚きました。
もし今回こうした取り組みをしていなかったら、そういった才能に触れる機会はなかったかもしれないと思うと、コンテストを企画してよかったと感じました。
瀬川さん:土地柄としてそこまで日本の漫画に強い印象があったわけでもなく、まさかそんな地域から、レベルの高い応募が来るとは思っていませんでした。富崎さんの言うように、本当に予想外でしたね。

KADOKAWA 出版グループ グローバルコミック部 部長 兼 グローバルコミック編集部 課長 兼 編集長 海外事業グループ 海外マンガ編集部 課長 兼 編集長 瀬川 昇さん
「漫画を作るプロセス」を伝えたYouTube動画がコンテストの認知拡大に寄与
── 初開催にもかかわらず、グローバルにコンテストのことが届いた要因は何だと思いますか?
富崎さん:描き手にしっかりリーチできたのが大きいと思います。今回、認知拡大に一番寄与したのは、海外向けインフルエンサーマーケティングの支援事業を行うグループ会社のGeeXPlusに協力をお願いしたYouTubeの動画です。
日本のコンテンツが好きでかつ絵も描ける、登録者数300万人以上の人気YouTubeチャンネルを運営する海外クリエイターの方々にネーム※ を書いてきてもらい、そのネームに対して編集者がアドバイスするという内容でした。
※漫画を描く際の設計図のようなもので、コマ割り、構図、セリフなどを大まかにまとめたもの
「実際に普段作家と編集者がどのようなやり取りをして、どのように漫画が作られていくのか」を見せた動画でしたが、公開後にはサイトのPV数がそれまでの10倍以上に跳ね上がり、問い合わせの数も数日間で3桁以上来るほどの反響がありました。
岡村さん:コンテストへの関心の高さを実感したのは、ニューヨーク・コミコン(NYCC)で実施したパネル講演で、漫画の描き方講座を行った時のエピソードです。当日はそこまで人が集まらないのではと思っていたのですが、実際には約300人ほどの参加者が詰めかけ、会場の部屋が満席になるほどの盛況ぶりでした。さらに講演後には、ポートフォリオレビュー(持ち込み原稿にアドバイスを行うもの)の受付も行ったのですが、これも予想に反して長蛇の列ができるほどの反響があり、現地の熱量を肌で感じることができました。
グローバルにおける受賞作家の出口戦略を確立して「世界編集部構想」の実現を目指す
── 最後に今後の展望を教えてください。
岡村さん:コンテスト自体はこちらの予想を大きく上回る反響で、世界中から優れた作家と出会える貴重な機会にもなったと感じており、今後もこの取り組みをさらに発展させていきたいと考えています。

海外事業グループ North America and Europe Headquarters 兼 グローバル電子書籍事業室 岡村 華子さん
現状は今回の成果を踏まえ、第2回の開催をどうするか検討中です。もし実施するならどういった位置づけで行うのかなどについて海外事業グループと出版事業グループで協議を進めている段階です。
富崎さん:今回はスピード重視でサイトを立ち上げたので、日英しか言語の対応ができませんでしたが、次回はさらに多言語で展開して、より多くの人にコンテストを周知できるようにしたいですね。そして、グローバルにおける受賞作家を漫画家デビューさせるための出口戦略も各編集部と協力してしっかりと練っていく予定です。
瀬川さん:今後取り組んでいくのは「入口の拡大」と「出口の強化」の2つです。まず入口の部分について、初開催で想定を超える応募数があったとはいえ、2回目以降も同様の応募数が見込めるとは限りません。特に英語以外の言語圏にどうアプローチしていくかは検証とチャレンジが必要になってくるので、より多くの応募者を集められる仕組みづくりに注力していきます。
出口については、受賞後の作家に編集者をつけて、言語面でのサポートもしていきながら商業作品として形にしていく流れを作っていきます。KADOKAWAは世界中にグループ会社や出版事業の拠点があるため、現地拠点との連携も強化しながら、日本側で作品開発を進め、現地市場へ直接届けるルートを確立していく予定です。
今後の展開として、まずは今回の受賞者の連載を約束してくれている各コミック編集部に対して2026年9月までに受賞者の連載作品を書籍化する目標を設定しており、その実現に向け準備を進めていきたいと思います。その後、最終的には世界に広がるKADOKAWAグループの各社で同じ意思を持って作品がつくられていく、あえて言うならば「世界編集部構想」の実現に繋げていくのが理想ですね。
※本記事は、2025年7月時点の情報を基に作成しています